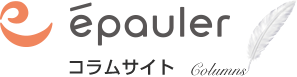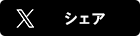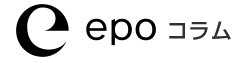日本一の大きさを誇る出雲大社の大しめ縄をはじめ、全国各地の神社にしめ縄を奉納している飯南町の職人集団・「飯南町注連縄企業組合」の匠たちの技を紹介する施設。しめ縄作りのほとんどの工程が見られるほか、職人直々の指導で可愛いしめ縄グッズを作ることもできる。
~ 目次 ~
小さな「しめ飾り」から出雲大社の「大しめ縄」まで自由自在! しめ縄造りの匠たちの技を知る。
神社やお寺に掲げられている、見事なしめ縄。
特に出雲大社 神楽殿(いずもたいしゃ・かぐらでん)の「大しめ縄」が有名ですが、そんな驚異の職人技を間近で見られる施設があります。
『大しめなわ創作館』。
中国山地の中央付近、広島との県境に位置する飯南町(いいなんちょう)で、町に伝わる「しめ縄文化」を紹介している工房兼観光施設です。
常時12~3人の職人がしめ縄作りにいそしんでおり、標高500メートルの高原で育てた強くてしなやかなワラを材料に、大小様々なしめ縄を作っています。
秘伝のしめ縄作りの工程をほぼ全て見学できるほか、飯南町のしめ縄作りの歴史を豊富な資料と実物で紹介。さらに職人が直接手ほどきしてくれる「手作りしめ縄体験」では、ファンシーで可愛いしめ縄グッズを作ることができます。
 しめ縄とは、神様の領域と人の領域を隔てるために張る縄。そんな神聖な伝統を間近で見て、触れて、体験できる。
しめ縄とは、神様の領域と人の領域を隔てるために張る縄。そんな神聖な伝統を間近で見て、触れて、体験できる。
 『大しめなわ創作館』の建物。出雲大社の神楽殿の設計者による設計で、出雲大社の御本殿の御神座(ごしんざ/神様がいる場所)と同じく西向きに建っている。
『大しめなわ創作館』の建物。出雲大社の神楽殿の設計者による設計で、出雲大社の御本殿の御神座(ごしんざ/神様がいる場所)と同じく西向きに建っている。
『大しめなわ創作館』で見たり体験したりできるのは、以下の3つです。どれも「大しめ縄の町」飯南町ならではの貴重なもので、神社や職人技に興味のある方は必見です。
●展示スペース
出雲大社の大しめ縄の制作工程や、その奉納風景の写真パネル、出雲大社の大しめ縄に下げられているものと同じ大きさの「大しめのこ(しめ縄に吊り下げる円錐形の飾り)」など、しめ縄に関する様々な展示が見られます。
●しめ縄制作工房(見学可)
館内にある、職人たちの工房です。全国の神社などから依頼されたしめ縄を制作しており、その現場を間近で見学できます。
●手づくりしめ縄体験
熟練のしめ縄職人が直接手ほどきしてくれる、貴重な手作り体験。簡単なものから本格的なものまで、希望に合ったしめ縄グッズを作れます。
 しめ縄作りの伝統と技を知り、日本の稲作文化から生まれた「稲わら文化」に触れられる。
しめ縄作りの伝統と技を知り、日本の稲作文化から生まれた「稲わら文化」に触れられる。
雪深い山里で育まれたワラ細工としめ縄作りの歴史。
『大しめなわ創作館』がある飯南町は、中国地方有数の豪雪地帯です。そのため雪に閉ざされる冬の間の手仕事として、ワラ細工作りが盛んに行われてきました。
蓑(みの)・草鞋(わらじ)・雪靴などなど、多くの生活必需品をワラだけで作り上げる手技。それは「しめ縄作り」の格好の基盤となって、その技術へと発展していったのです。
そして昭和30(1955)年代に、出雲大社の分院が飯南町にあったことがご縁となって、その信者と住民たちが協力しあい、大しめ縄を制作・奉納。さらに昭和56(1981)年には、出雲大社の神楽殿が建て替えられたのを機に、さらに巨大なしめ縄を奉納しました。そして現在に至るまで、出雲大社の大しめ縄を7~8年ごとに作りかえては奉納しています。
 昭和56(1981)年に出雲大社に奉納された大しめ縄。現在の大しめ縄は平成30(2018)年に奉納されたもので、その大きさはなんと長さ13.6メートル・重さ5.2トン!
昭和56(1981)年に出雲大社に奉納された大しめ縄。現在の大しめ縄は平成30(2018)年に奉納されたもので、その大きさはなんと長さ13.6メートル・重さ5.2トン!
 その他にも、出雲大社に次ぐ大きさを誇る茨城県の出雲大社 常陸分院の大しめ縄や、東京都港区の秩父宮ラグビー場など、全国各地にしめ縄を奉納している。さらに福岡県・宮地嶽神社の大しめ縄については、棟梁の石橋真治(いしばし・しんじ)氏が現地で最終工程の「大よりあわせ」を指導。名実共に日本一の「大しめ縄職人の里」として知られている。
その他にも、出雲大社に次ぐ大きさを誇る茨城県の出雲大社 常陸分院の大しめ縄や、東京都港区の秩父宮ラグビー場など、全国各地にしめ縄を奉納している。さらに福岡県・宮地嶽神社の大しめ縄については、棟梁の石橋真治(いしばし・しんじ)氏が現地で最終工程の「大よりあわせ」を指導。名実共に日本一の「大しめ縄職人の里」として知られている。
 飯南町は出雲大社とその主祭神・大国主大神との関わりが深い。町の名峰・琴引山には大国主大神の神宝の琴が納められていると伝わっており、10月の「神在月」には全国八百万(やおよろず)の神々がここに降臨して、川を下ってから海を経て、出雲の稲佐の浜(いなさのはま)に上陸する、と言われている。
飯南町は出雲大社とその主祭神・大国主大神との関わりが深い。町の名峰・琴引山には大国主大神の神宝の琴が納められていると伝わっており、10月の「神在月」には全国八百万(やおよろず)の神々がここに降臨して、川を下ってから海を経て、出雲の稲佐の浜(いなさのはま)に上陸する、と言われている。
(琴引山の中腹にある「大神岩」)
 しめ縄作りのために育てられている、専用の稲。
しめ縄作りのために育てられている、専用の稲。
しめ縄に適したワラ作りから、町ぐるみで取り組む。
『大しめなわ創作館』で使われているワラは、飯南町内の田んぼで育てられています。
品種は「赤穂もち」という古代米のモチ米と、明治時代に島根県で発見された「亀治」と言うウルチ米(ご飯として食べられている普通のコメ)。
いずれも背丈が高く、さらに稲に実が入ると曲がってしまうので、葉が青くて真っ直ぐなうちに刈り取って乾燥させます。
そのワラの根本を覆っている「ハカマ」を1本1本取り除いて、さらに太さごとにより分けるなどして、ようやくしめ縄用のワラが用意できるのです。
こうした大変な手間ひまをかけて、飯南町の「しめ縄」は作られています。
 飯南町の風景。標高が高く寒暖差が激しい高原で、コシのしっかりした丈夫な稲が育つ。
飯南町の風景。標高が高く寒暖差が激しい高原で、コシのしっかりした丈夫な稲が育つ。
 しめ縄作りの工程は、ワラの選別・菰(コモ/しめ縄の中芯を巻くために編まれるワラ束)編み・菰繋ぎ・より合わせ・など非常に多数。それらを黙々とこなしながら、1ヶ月に2、3本のペースでしめ縄を作り上げている。
しめ縄作りの工程は、ワラの選別・菰(コモ/しめ縄の中芯を巻くために編まれるワラ束)編み・菰繋ぎ・より合わせ・など非常に多数。それらを黙々とこなしながら、1ヶ月に2、3本のペースでしめ縄を作り上げている。
 普通の神社用のしめ縄の大きさは、長さ3m60cm~4m、直径40~50cmほど。それらに加えてお土産用の小さな「輪じめ」なども作っている。
普通の神社用のしめ縄の大きさは、長さ3m60cm~4m、直径40~50cmほど。それらに加えてお土産用の小さな「輪じめ」なども作っている。
 しめ縄は、本来は神社の氏子(うじこ/神様を信仰する人々)が作るもの。だが少子高齢化などによって氏子が減り、その伝統の維持が困難な神社が増えている。そういった神社などに依頼されて、全国各地にしめ縄を納めている。
しめ縄は、本来は神社の氏子(うじこ/神様を信仰する人々)が作るもの。だが少子高齢化などによって氏子が減り、その伝統の維持が困難な神社が増えている。そういった神社などに依頼されて、全国各地にしめ縄を納めている。
縁起の良いしめ縄を自分の手で作ろう!
匠の技のすごさを知った後は、ぜひ職人直々に指導してくれるしめ縄作りにチャレンジしてみましょう。
『大しめなわ創作館』では、午前の部(10:00~11:30)と午後の部(13:00~16:00)の1日2回に分けて、しめ縄づくりの「体験メニュー」を行っています。
全国に名だたる職人達の手ほどきで、可愛く縁起の良いしめ縄を作れます。
■初級コース (所要時間:30~40分/体験料金:980円)

直径10cmほどの小さな「輪じめ」を作って、お好みの短冊を取り付ければ完成です。可愛い和のリースとしてインテリアやプレゼントに最適です。
■中級コース (所要時間:40~60分/体験料金:2,200円)
ご家庭の神棚やお正月の飾りなどに使える、長さ30cmほどのしめ縄を作ります。
■デコレーション コース (所要時間:40~60分/体験料金:2,700円~)

中級コースと同じしめ縄に、造花やリボン等でデコレーションするコースです。
ゴージャスな和リースとして、とっておきの想い出とお土産になります!
※いずれのコースも来館後に要受付(混雑しだいで体験できない場合があり)
※10名以上の手作り体験は要・事前予約
※12月は休止(お正月用のしめ縄作り等で繁忙期のため)
 丁寧な指導でお子様でも安心!
丁寧な指導でお子様でも安心!
日本全国からしめ縄をオーダーできる!
さらに『大しめなわ創作館』では、様々な種類のしめ縄や、しめ縄のアレンジ製品などを販売しています。
神棚用のしめ縄などの古式ゆかしい伝統品をはじめ、リース調の和モダンなデザインも可能。各種お祝い事や結婚式の引き出物などに好評です。
価格は2,000円〰1万円ほどで、ご要望に応じて特注もできます。
そして毎年12月には、お正月用の「しめ飾り」を販売。
もちろん神社の拝殿や鳥居・ご神木などに掛ける大きなしめ縄の注文も受け付けていて、神社や地域ごとの伝統に合わせてきめ細かに対応してくれます。
全てが手作りで、同じ物がひとつとしてない真心のこもった「しめ縄」。
この上ない縁起物を見て、触れて、日本の伝統と文化に思いをはせてみてはいかがでしょうか?
 自宅や会社の神棚に、特別な贈り物に。由緒正しいしめ縄が格調を添える。
自宅や会社の神棚に、特別な贈り物に。由緒正しいしめ縄が格調を添える。

- DATA
飯南町 大しめなわ創作館
HP:https://ohshimenawa.com/
住所:島根県飯石郡飯南町花栗54番地-2 (「道の駅とんばら」向かい)
電話:0854-72-1017
営業時間:10:00~17:00
休館日:12/29頃~1/4頃
入館料:無料
取材協力・
写真提供:
飯南町 大しめなわ創作館/無断転載禁止
ライター:風間梢(プロフィールはこちら)
Related Posts
関連記事