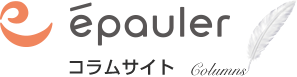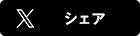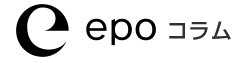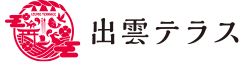ヘルメットをかぶる機会が多い女性にとっては、髪型が崩れるkとに悩んでいないでしょうか?
必ずといっていいほどヘルメットをかぶれば髪型が崩れるため、「今日は自転車やバイクの使用はやめておこう」と考える人も少なくないでしょう。
そこでヘルメットをかぶっても、髪型を崩れにくくする方法について解説しています。
ヘルメットをかぶる機会が多く、髪型を気にする人は参考にしてみてください。
ヘルメットで髪型が崩れる原因

自転車やバイクに乗る時には、必ずヘルメットをかぶらないといけません。
ところがヘルメットをかぶると、以下の2つの原因によって髪型が崩れます。
- ヘルメットで髪型が崩れる原因
-
- 頭が蒸れて髪型が崩れる
- ヘルメットで髪が崩れる
実際にNHKが行った「ヘルメットをかぶりたくなくなる理由」についてのアンケートを確認すると、3人に1人ほどの人が「髪型が崩れること」だと答えています。
東京都が、2023年に行ったアンケートでは、ヘルメット未着用の人が着用しない理由として挙げたのは、「着用が面倒」が47.9%で最も多く、次いで「駐輪時に置き場所がなく荷物になる」が38.6%、「髪型が崩れる」が31.8%、「頭が蒸れたり熱がこもる」が29.8%となっています。
※引用:NHKより
これらの原因を踏まえても、ヘルメットをかぶりたくないと感じるのもわかります。
ところが原因に合わせた対策ができれば、髪型が崩れるのを軽減できるため、これから紹介する内容をうまく活用してみましょう。
ヘルメットが原因で崩れる髪型の対策
上記で紹介した髪型が崩れる原因を参考に対策するだけでも、髪型が乱れるのを予防しやすくなります。
- 原因に合わせた対策
-
- 物理的に崩れた時の対策
- 蒸れによる対策
ただし、これから紹介する対策を実践できたとしても、100%髪型が崩れないとは言い切れません。
「ヘルメットをかぶれば崩れない髪型はない」という点だけでは、覚えておいてください。
対策《1》物理的に崩れた時の対策

まず、ヘルメットで髪型が崩れる原因は、物理的に髪型が潰れるという点です。
ヘルメットは重いものが多く、その重みで髪型が潰れてしまうため、これを軽減できる対策を意識してみましょう。
大きく分けて2つの対策が考えられます。
- ヘルメットの対策
-
- 崩れにくい髪型を選ぶこと
- ヘアアイテムでカバーすること
この2つのポイントを意識して、以下の内容を参考にヘルメットをかぶってみてください。
少なくとも、髪型が崩れる大きな原因として挙げられるポイントは、「風による乾燥」と「湿気で髪型が崩れること」です。
この2つのポイントを意識して、以下の内容を確認してみましょう。
崩れにくいおすすめの髪型
ヘルメットをかぶる時に、髪型が崩れるのが気になる人は髪型を変えましょう。
以下の2つの髪型がおすすめです。
- 髪型選びのポイント
-
- ロングヘアの場合:簡単にまとめられるアレンジ
- ショートヘアの場合:ナチュラルに見えるヘルメットヘアの工夫
まず、ヘルメットをかぶった時の状況を見てみましょう。
ヘルメットをかぶる時には、少なくとも屋外で使うケースがほとんどではないでしょうか?
屋外に長時間いる時には、風の影響を大きく受けます。
特に、自転車やバイクに乗る時には、風に長時間さらされるため、毛先が乾燥し、これがパサつきの原因となってしまいます。
ロングヘアの際は、髪をまとめて外気に晒されにくくしてください。
例えば、毛先を服の中に入れておき、ヘルメットを脱ぐ時に服の外に出しましょう。
それだけでも毛先の乾燥はカバーできます。
ところが中途半端な長さのミディアムヘアだった場合、服の中に毛先を入れられません。
その結果、毛先のパサつきがひどくなったというケースも出てくるでしょう。
だからこそ、外気にさらされにくい「ショートヘア」や「ロングヘア」はちょうどいい髪型です。
また、ショートヘアの場合は、ヘルメットの重みで潰れてしまいます。
そこで潰れても自然に見えるナチュラルヘアにしておくと安心です。
パーマヘアなどのヘアセットを前提とした髪型は、ヘルメットをかぶる予定の人ほど控えておきましょう。
おすすめアイテム
ヘルメットをかぶる時には、髪型と同時に、ヘアアイテムを揃えておくと安心です。
- ヘルメットをかぶる時のおすすめアイテム
-
- ショートヘア:ワックスで髪型をセットしなおす※セット力の高いものだと束感が出やすい
- ロングヘア:毛先にパサつきをカバーできるヘアオイルなどの保湿力の高いアイテムを使う
- ヘアセット用アイテム:ヘアブラシやコームを持っておくのもおすすめ
髪型が崩れる予防用アイテムとして、上記のものを持っておきましょう。
特に、ヘアコームやブラシは必須です。
髪型を整えておいてからヘルメットをかぶる癖をつけておくと、脱いだ後の髪型に大きな違いが出せます。
対策《2》蒸れによる対策

ヘルメットをかぶれば、重みによって髪型が潰れるだけでなく、汗などの湿気によっても髪型が崩れます。
- 蒸れによる対策の一例
-
- 汗や湿気に対する吸湿性対策
- 汗によるべたつき対策
- ヘルメット選びも大事
※参考:頭と顔の汗がすごい理由は?髪の毛のべたつきが気になる汗かきの人のための対策
このように、ヘルメットをかぶるだけで、様々な蒸れを起こしてしまいます。
そこで、以下のアイテムを持っておき、その都度蒸れ対策をしておきましょう。
- 蒸れ対策におすすめのアイテム
-
- 通気性の良いヘルメット
- ヘルメットインナーで蒸れ防止
- かぶった後はドライシャンプーで汚れを除去
ヘルメットインナーとは、ヘルメットをかぶる前に付けるアイテムです。
例えば、シリコン製のインナーヘルメットをかぶっておくと、ヘルメット内部に少しだけ空間を作ってくれるため、髪型が崩れにくくなります。
さらに、通気性の高いヘルメットを使えば、それだけで蒸れ対策になるでしょう。
極めつけは、ドライシャンプーです。
洗い流す必要がないため、ヘルメットを脱いで蒸れを感じた時に使うだけで、皮脂汚れをケアできます。
ヘルメットで崩れやすい髪型も予防できるヘアケア方法
ヘルメットで髪型を崩しにくさを高めるためには、普段のヘアケアのやり方も深く関わっています。
髪をきれいにする習慣を身につけておくと、髪型が崩れにくくなるため、以下の方法を参考に普段のヘアケアを見直してみてください。
ふんわり感を出すためのシャンプー選びは重要

ヘルメットをかぶってもふんわり感をキープさせるためには、シャンプー選びが重要になります。
以下のポイントを意識してシャンプーを選んでみてください。
- シャンプー選びのポイント
-
- 洗浄力が高めの洗浄成分を選ぶ
- シリコンなどのコーティング成分が多いシャンプーは控える
シャンプー選びで重要になる点は、洗浄成分とシリコンなどのコーティング成分です。
一般的にはアミノ酸洗浄成分などの、洗浄力を控えめのシャンプーがいいとされています。
ところが、ヘルメットをかぶった時には、それが裏目と出て髪型が潰れてしまうため、できるだけふんわりしやすい洗浄力が少し強いシャンプーを選びましょう。
※参考:シャンプーは洗浄成分で変わる!正しい選び方とそれぞれの特徴まとめ
また、せっかく洗浄力が高めのシャンプーを選んでも、コーティング成分が多いと、同様に髪型が潰れやすくなります。
少なくともノンシリコンシャンプーを選べば、髪の重みが少なくなるでしょう。
風による毛先のパサつき対策はトリートメント選びでカバー

シャンプーに関しては、頭皮や髪の毛の根元がふんわりしやすくなりますが、毛先に対してはトリートメントでカバーしましょう。
ヘルメットをかぶる環境下では、毛先が乾燥しやすい状況が増えます。
だからこそトリートメントで毛先を保湿してください。
- トリートメント選びのポイント
-
- シリコンなどのコーティング成分で風からの乾燥をカバー
- 保湿成分で髪内部の水分を減らさない
- ヘアダメージがあるなら加水分解ケラチンなどで補修しておく
シャンプーでは、シリコンが入っていないものを選んでほしいと紹介しましたが、トリートメントについてはシリコンなどのコーティング成分が多いほうが安心です。
さらに、保湿成分で髪内部の水分量をキープさせ、ダメージがある部分を補修成分で補ってしまえば、毛先の乾燥を予防できます。
※参考:ひどく傷んだ髪に市販トリートメントは効果あり?サロン系との違いと使い分けの方法
ヘアカットできれいな髪型をキープさせることも大事になる

シャンプーやトリートメントで、髪の状態がきれいにキープできない時には、ヘアカットを活用しましょう。
特にダメージがひどい毛先はトリートメントで補っても、パサつきがおさえられないケースがあります。
ヘアカットをすれば、そんな毛先を切り落とせるため、ヘルメット対策が容易となります。
きれいな髪型をキープしやすくするため、以下の記事を参考に、髪型を変えてみてはいかがでしょうか?
少なくとも、ショートヘアなら4週間に1回、ロングヘアなら、2ヶ月に1回程度の頻度でカットをすれば、髪型をきれいな状態でキープできるはずです。
※参考:40代女性がカットのみで悩みは解決できる?おすすめの髪型はショート!
ヘルメットをかぶる機会が多くても崩れやすさは髪次第

ヘルメットをかぶれば、誰でも髪型が崩れますが、その状態をおさえる方法はあります。
それは普段のヘアケアや髪型選び、ヘルメットなどのアイテム選びです。
ヘルメットをかぶれば、重みによって髪型が潰れる上に、風や湿気によって毛先のダメージがひどくなります。
これらを上記の方法でカバーできれば、きれいな髪型をキープしやすくなるでしょう。
ヘルメットをかぶる機会が多い人ほど、注意して対策をしてみてください。
Related Posts
関連記事